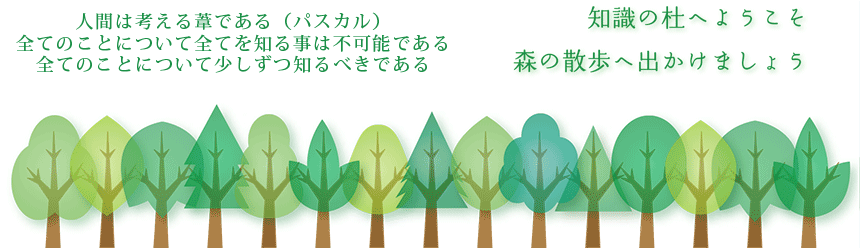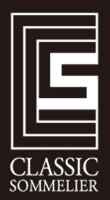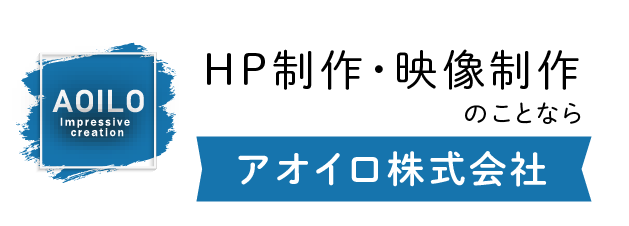グローバル経営戦略とビジネスインテリジェンス
―ビジネスインテリジェンスの活用法 ―
Global Business Strategy and Business Intelligence
-Management of Business Intelligence-
中川 十郎 1)
要旨
ビジネス インテリジェンス (高度経済、経営情報)のグロ―バルビジネス、経営戦略への適用に関し、その歴史とグローバル経営戦略への活用について具体的事例を基に、これまでの32年間、183回(研究会参加者累計16,000人、講師累計(600人)の「日本ビジネスインテリジェンス協会」(Business Intelligence Society of Japan) での研究成果を基に、論考する。
キーワード:ビジネスインテリジェンス、グローバルビジネス、情報の収集、分析、活用、リスクマネージメント、
危機管理、情報の機密保持、ビジネスインテリジェンス理論、情報監査、AI、ChatGPT
1はじめに
日本では情報に対する研究が欧米諸国に比べ、遅れている。また情報分折、活用も政、官、学、財界においても諸外国に比べ、大幅に遅れている。情報はただとの認識で,情報(Information)と情報を分析、付加価値を付けたインテリジェンス(Intelligence)の違いも認識が希薄である。
BIG DATA, AI(人工知能)、Chat GPTが急速に広まり、さらにSNSが氾濫、Fake Newsも拡大している。
そのような現状下、情報、とくにビジネスインテリジェンス(高度経済、経営情報)の収集、分析、活用法の習得は、高度情報化時代を迎え、必須となりつつある。
以下、特にグローバル化時代のビジネスインテリジェンス活用について、実例も交えつつ論じたい。
インテリジェンス、情報論の観点から見た場合、官民とも政策決定に際し、その意思決定の基礎、基盤となるべき情報、すなはちインテリジェンスの収集、分析、活用が十分なされていないように見える。よって。我が国の政策決定や企業内外の経営戦略策定は不十分な情報と情報分析不足により危機的状況にあるといえよう。
古来、日本に於いては「空気」、「水」、「情報」はただとの意識が強い。それゆえ、情報収集に十分な資金、人材を投入せず、さらに収集した情報の情報源精査、情報分析、情報監査も十分しないまま、政官民とも安易に政策決定をしている傾向が強い。
2.日本の三つの敗戦、「武力敗戦」、「金融敗戦」、「情報敗戦」
日本は過去、三つの敗戦を経験している。一つ目が太平洋戦争での1945年の「武力敗戦」である。
特に、ミッドウエー敗戦は旧日本海軍の情報敗戦の典型例とみなされている。情報を軽視し、精神力で戦った日本軍に問題があったと思われる。
二つ目が1990年代からの我が国経済の長期低迷で、これは「経済、金融敗戦」である。90年代以降、実に30年にわたり、日本経済は低迷を続け、経済学者の野口悠紀雄氏などは著書『日本が先進国から脱落する日』や、投資家のジムロジャース氏も『捨てられるに日本』でこのままでは日本は衰退するばかりで立ち直れないのではと日本の将来に対し悲観的な見方である。さらに2008年のリーマンショックは日本経済衰退に追い打ちをかけ、日本の不動産、とくに、主要銀行に壊滅的打撃を与え、主力銀行は生き残りのために軒並み合併に追いこまれた。
かって、日本は1980年代後半、筆者のニューヨーク駐在時代、米国を追い詰め、世界で1~2位の競争力を有していた。GDPでも米国に肉薄し、世界第2位の地位を占めていた。しかし、2001年にWTOに加盟し、経済成長、貿易が拡大した中国に2010年に追い抜かれた日本は現在、中國にGDPで4倍以上の差をつけられ、差は急速に拡大しつつある。GDP per Capitaでもシンガポールや台湾、韓国にも追い抜かれつつある。
一方、2023年4月に人口で中国を抜き去り、GDPで22年に旧宗主国の英国を追い抜いたインドは世界第5位に躍進。さらにインドはグローバルサウスの盟主とし23年9月のG20会議を議長国として成功させた。この勢いで2025年にはGDPでドイツを、2027年には日本も抜き去り、米国、中国に次いで世界第3位の経済大国に躍進するとみられている。
かってハーバード大学教授のエズラ・ボーゲルに「ジャパン アズ No.1」と喧伝された日本は衰退の一途にある。しかし日本は官民ともに危機感がなく、東海の小島で太平の夢をむさぼっている情けない状態にある。
三つ目の「情報敗戦」の典型的な例は2011年3月の「福島原発事故」、さらに2019年から流行した「コロナ禍」への対応例である。東京電力は地震への対応をおろそかにし、「危機管理」対策に致命的失敗を犯した。
危機管理の要諦は迅速な情報収集と分析、活用にある。
福島原発事故の対応を見ると、すべてが後手、後手にまわり、十分な情報に基づいた対策がとられていない。情勢判断、対策の基礎となる情報、特にインテリジェンス入手が不十分で、重要な致命的情報を迅速に収集しようとの努力もなされていなかったように見える。日本政府関係機関、東電の連携による政府中枢との迅速な情報収集、分析、意思決定が組織的に機能していなかったのではないか。十分な情報がないまま政策、対策を立てるに際し、情報収集やその情報に基づきだれが対応策の決定をしたのか、はっきりしない。
CIO(最高情報責任者)はだれで、どういうルートから情報を吸い上げ、だれが責任をもって、その情報を分析し、最終意思決定を行ったのか、不明である。
原発危機に際し、政策、対応、決定のための我が国の国家情報システムはいかに作動したのか。原発事故後、その情報収集、伝達、分析、政策決定に関する十分な検証がなされていないのではないか。国家情報システムの検証と、必要により、早急なる再構築が望まれる。
危機管理に際しては、まず迅速な情報収集と、その情報分析、活用が肝心である。十分な情報なくして危機管理は不可能である。事故が発生してから、応急、対策を行うのではなく、事前に十分に情報を収集し、それを基に予防措置を講ずるのが危機管理の要諦である。
以上の観点から東京電力の対応を見ると、リスク管理、危機管理体制が十分に構築されていなかったのではと推察される。原発事故は国民の健康に甚大な影響を与える。
今回の原発汚染水(政府は処理水と言っている)の海中への放出に関しても、危惧を抱いた太平洋諸国家、中國、韓国などアジア諸国への説明と了解取得が十分になされたとはいえない。日本の一方的かつ早急な放流は一考の余地があると思われる。 ここでも情報の収集、分析、配布が重要であることを十分に認識すべきであろう。
一方、コロナ禍に関しても情報の収集、分析、配布について情報論的に種々問題がある。コロナ対策にいても情報の一元管理が十分でなく、また政府関係機関連携に問題があった。さらに感染者などの集計に関しても、感染者や感染情報をFaxで送付するなどAI時代に前近代的な対応がなされていたことが明らかになり、厚生省をはじめとする日本の医療機関のIT化が諸外国に比べて極端に遅れていたことが判明した。
これに比し、諸外国、中でも台湾の医療関係情報システムが進んでいることは大きな関心を呼んだ。
一方、日本の医療研究が遅れていることも明らかになった。コロナワクチン開発に於いても大幅に出遅れており、国産ワクチンはなく、欧米から高価なワクチンを大量に輸入せざるを得なかった。
これに比し、欧米に加え、中國、ロシア、なかでもカリブの医療先進国キューバが2種類のワクチンを開発。発展途上国に供給したことは大きな話題を呼んだ。
日本のイベルワクチンはアフリカやインドでも関心を呼んだとのことだが、なぜ日本で活用されなかったのか、精査する必要があるのではないか。
さらに情報論の観点からみると日本政府のワクチン購入は、国民の税金で輸入されているもの故、購入価格、購入数量、廃棄された数量、在庫数量など国民に公開すべきであると思われる。
あわせ日本独自のワクチンも将来に備え、国家戦略として早急に開発に全力を挙げるべきだと思われる。
以上、「福島原発事故」、さらに「コロナ禍」では「武力敗戦」、「経済・金融敗戦」の教訓が生かされておらず、我が国は三度「情報敗戦」の瀬戸際にある。その対応には情報を十二分に収集し、それを分析、活用するインテリジェンス力が強く求められている。
3.情報化時代の機密保持
次に情報化時代に盛んになっているサイバー攻撃を避けるためにも情報の機密保持が非常に重要である。機密保持に関連し、具体的理論を下記紹介したい。
ビジネス インテリジェンスの重要な役割の一つに「情報の機密保持」がある。インテリジェンスのグルと目されたスエ―デン・ルンド大学ステバン・デジエル博士は1970年代初めに世界で初めてルンド大学に「ビジネスインテリジェンス」講座を開設したことで有名である。デジエル博士の講座ではまず冒頭に「情報の機密保持」を強調し、重視した。
インテリジェンスの重要な役割の一つに「情報の機密保持」がある。最近の度重なる日本政府や日本企業へのサイバー攻撃でもわかる通り、「機密情報防衛」は「経済安全保障」、「的所有権保護」とも関連し、高度情報、知識社会において企業、国家にとっても最重要な課題である。
2013年11月2日ロンドンで開催されたサイバー空間に関する国際会議でサイバー犯罪を「経済、社会福祉に対する深刻な脅威」と認定し、政府間の信頼構築へ努力すること」を議長声明で確認した。
1996年には米国は有名な「経済スパイ法」(Economic Espionage Act=EEA)を策定し、経済スパイへの重い罰則を導入した。一方、アングロサクソン諸国は1940年代からスパイ衛星を活用し、Echelon(梯子の隠語)盗聴システムを稼働させ、軍事情報のみでなく、経済情報も盗聴しているとして、欧州議会でも批判の的になった。(『知識情報戦略』24~25ページ)。インテリジェンス戦略に於いては、戦略確立のためのAggressive Intelligence(攻撃的情報)のみならず、防御的情報(Defensive Intelligence)の研究も重要である。
グローバル時代の経済競争は熾烈な情報戦でもあることを認識し、インテリジェンス、情報を最大限に活用する方策を研究することが肝要である。 日本では情報機密保持がずさんで、ゆるく、日本はスパイ天国と見られている。過去、日立・三菱電機~IBM、富士通~AMDAL,ミノルタ~Honeywell。東芝機械の工作機械の対ソ輸出問題、 CCI(クリーブランド医学研究所)でのアルツハイマーバイオ試薬事件など枚挙にいとまがないほどである。
東芝機械については高性能工作機械をソ連へ輸出したことで、ソ連潜水艦のプロペラの消音が実現し、追跡が困難となった。これは、共産圏向け輸出を規制しているココムに違反しているとして米国は東芝の米国向け輸出の1年間の禁止、米国主要新聞に謝罪広告の掲載を要求した。しかし、後日、ソ連潜水艦のプロペラの消音は東芝機械の輸出前から実現していたことが判明。東芝はあらぬ濡れ衣を着せられたのである。
CCIバイオ事件でも、域外管轄の日本人研究者を逮捕し、裁判にかけた。これは上記米国経済スパイ防止法(EEA)の外国人に対する初の適用となった。しかし実情については不明な点があり、問題となっている。
先年、問題となった中国ファーウエイの副会長拘束、ファーウエイ通信機器が盗聴に使用される危険があるとして米国からの締め出し、半導体製造機器、先端半導体の中国向け輸出禁止など、かっての日本の自動車などの米国輸入規制など、1980年代をほうふつさせるものがある。
4.グローバルビジネスとビジネスインテリジェンス、競争情報
経済のグローバル化が急速に進み、国際ビジネス競争が激化し始めた。冷戦の崩壊で、世界の有効需要が10億人から30億人に拡大し、自由主義圏、旧共産圏の市場競争と国際ビジネス競争がし烈になり始めた。
1986年になると米国SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals=競争情報専門家協会)がバージニアに元CIA諜報関係者などを中心に設立され、競争相手の情報収集の研究が始まった。かかる状況下、欧米 では米英を中心に競争情報の研究が急速に進み、現在もSCIPは毎年、米国を中心に世界主要国で競争情報研究会を開催している。
以下ビジネスインテリジェンスを理論面から考究する。
- ビジネスインテリジェンス情報理論
情報とは;① 情報、データ、
②インテリジェンス(付加価値情報)
情報の種類: ① 公開情報(40%)、②私的情報(60%)
③秘密情報(約3%)
情報の特性;与えても低減しない。(中川情報理論)
情報理論;
Herbert E. Meyer; ① 情報レーダー理論
②情報製油所理論
Ben Gilad; ① 情報濾過(コーヒー濾過)理論
中川 十郎 ;① 情報グルメ理論
②情報水力発電所理論
③ 情報3倍、3乗(Triple) 理論=
3倍蒐集、圧縮1・3理論
情報の活用;① 既存ビジネスの深化、拡大、新規ビジネスの創出
②リスク。危機管理
③情報の機密保持
情報監査 (Intelligence Audit)情報・情報源の評価、
情報の成果評価、cf (財務監査)
情報連鎖管理(Intelligence Chain Management-{ICM}
―目標設定~戦略作成~情報収集、情報選別 ~情報源信頼性チェク~情報分析、~情報評価~情報配布~情報活用~情報監査~成果レビュ- ~新目標設定(インテリジェンスサイクル)~このサイクルを連鎖することによって、情報の質を高めていく。~(CIAの手法)
情報処理システム:過去・現在・未来情報連鎖理論(中川PPFC理論)
過去の情報+現在の情報=未来予測
情報連鎖3C理論:
「関連付け」=Correlation, 「結び付け」≠Combination,「協力」=Cooperation
情報の歴史;
農業時代=「土地」が権力の基盤~10,000年前
工業時代=「資本」が権力の基盤~300年前(産業革命以降)
情報・知識時代=「情報・知識」が権力の基盤 (21世紀)
21世紀は情報・サービス、ソフト、データ、知識、AI(人工知能)が主導する時代となる。よって生涯教育、生涯学習、「リスキリング」が極めて重要となる。
「一生勉強、一生青春」の精神が大切。
国際化、情報化時代の日本の戦略;
- 情報、文化、創造性教育(学校、企業、官庁、政府)
- 国際語、Global Language 英語の教育が必須。(将来30億人が英語で交流できる時代が来る。(ケンブリッジ大学David Crystal 教授)
- 国際問題に関心を持つこと。
- 「情報化時代の今日、情報は毎日、世界中に氾濫しているが、インテリジェンス(付加価値の付けられた真に役立つ、価値ある情報)は砂漠の状態にある。」(Ben Gilad 元ラトガース大学准教授『グローバル時代の情報組織戦略』エルコ社(中川十郎ほか訳)
- 日々入手する情報を評価、分析し、付加価値をつけ、真に役立つ情報の活用法を学び、身につける努力を重ねることが、国際化、情報化、ChatGPT、AI 時代を生き抜くために最も重要な事である。
2) 情報収集・活用法
- 情報収集源;
新聞、経済誌、経済情報誌、業界紙、TV, SNS, Internet、 Blog,。Chat GPT, Social Media, 講習会、ZOOM参加、学会研究会、見本市、図書館、JETRO, 官庁、 地域会合、人的情報収集、
- 新聞情報では特に情報源、信憑性に注意し、関係情報の探索、2~3の情報源との比較、検証を心がけることが大切である。(情報監査が重要)
- 上記公開情報源に加え、人的情報を加味し、情報を重層的に深め、分析し、活用すること。
- 1週間、ひと月前の国内外のイベント、国際会議をモニターし、その対策を早めに打つこと。
- 国内外のマクロの情報から、世界や国内の動向を読み解き、ミクロの対策、戦略、戦術を樹立すること。
- 地図を逆さに見て、発想の転換を行い、普段と違った発想で、形にはまった日常性を打破する努力をし、斬新な発想と行動をとる。
例えば、日本中心の地図を欧州、アジア、米州、アフリカ、中近東、中央アジア、南米などを中心に据え、逆の立場から、地政学的に多層的、かつ複合的に情報を収集し、分析すること。
これは逆転の発想で、情報の客観性の確立、形にはまった日常性の打破に役立つ。
- 攻撃的情報(Aggressive Intelligence)をビジネスの確立、拡大に活用する。
- 防御的情報(Defensive Intelligence)はビジネスのリスク・危機管理、情報保全に活用する。
- 人間の五感全てを活用、情報を収集。活用する。
眼=色彩情報、TV、PC, スマホ、Chat GPT、Internet, 見本市、映画、演劇、読書などから情報を収集する。
口=話す、感情、情報提供、歌、食事、味情報を入手。
鼻=におい、アロマ情報。耳=聞く、音声情報、TV, スマホ、研究会、会議 ETC.
手=感触、触れる、タイプする、書く、ピアノ、楽器演奏、表現~現代社会では『眼』偏重の情報収集が主である。『目』の酷使。偏った五感の発達=情報社会の問題点
- 人的情報(Human Intelligence)の重要性=信頼できる人脈の確立が極めて重要である。情報感覚、情報セセンスを磨く努力が必要である。
- 情報収集に関しては他人よりも3倍多く人脈を構築し、他人よりも3倍多く情報を収集し、その情報を最大限に活用することが肝要である。
情報には ①公開情報、②人的・私的情報、③秘密情報 があるが、ビジネスには人的・私的情報が極めて重要である。人的、私的情報収集には信頼できる人脈確立が必須である。そのためには人に信頼される己の人格陶冶がまず第一に重要であることを強調したい。
以上
- 名古屋市立大学22世紀研究所特任教授、
日本ビジネスインテリジェンス協会会長・理事長
- 主要参考文献:。
『知識情報戦略』石川昭・中川十郎編著、(税務経理協会)2008年。『CIA流戦略情報読本』中川十郎ほか訳、(ダイヤモンド社)1990。
『グローバル企業の情報組織戦略』中川十郎ほか訳、(エルコ社) 1996年。『成功企業のIT戦略』、中川十郎他訳、(日経BP)2003年、
『国際経営戦略』中川十郎ほか共著(同文館) 1996年、『日本が先進国から脱落する日』野口悠紀雄(プレシデント社)2022年、
『2040年の日本』野口悠紀雄(幻冬舎新書)2023年、『捨てられる日本』ジム・ロジャース(SB新書)2023年、
『日本の絶望ランキング』大村大次郎(中公新書ラクレ、2023年
| 演 | |||