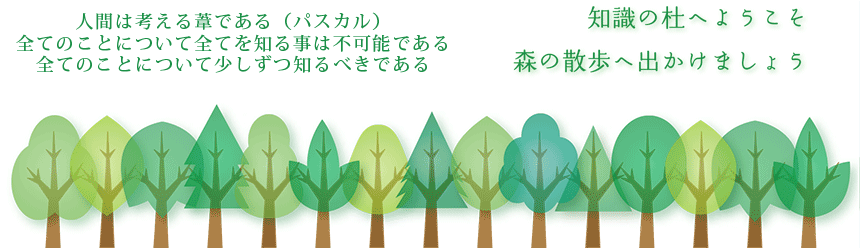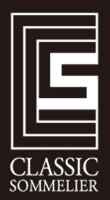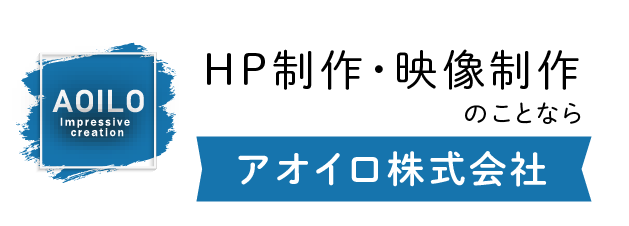BIS論壇No. 490『トランプ2.0』中川十郎2025年7月13日
1月20日のトランプ大統領が再登場以来6か月、矢継ぎ早に打ち出す高関税政策が世界を混乱に陥れている。そもそも米国一国主義で世界全体の貿易相手国に高関税を課すこと自体、戦後、米国が自ら打ち出したブレトンウッズ協定による世界銀行、IMF, GATT、1995年創設の世界貿易機関(WTO)の自由貿易の精神に反しているのではないか。
トランプ高関税政策に対し、中國をはじめ、グローバルサウスは対応策を模索している。
ブラジル・リオデジャネイロで7月6~7日 開催のBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中國、南アフリカの新興国グループ)に24年、イラン、UAE(アラブ首長国連連邦)、サウジアラビア、インドネシアなども参加。グローバルサウスで影響力を強めつつある。この会合を主催のブラジル・ルラ大統領は米国の高関税政策を批判。これに対しトランプ大統領は直ちにブラジルに50%の関税を課すなど、タリフマンぶりを発揮。発展途上国からは批判の声も上がっている。
6月にカナダ西部カナナキスで開催のG7会議は、トランプ大統領の会議中の退席、帰国で十分な成果を上げられず、G7の衰退を際立たせた。米国を除くG6の2,000年の
世界GDPに占める比率は35%から、24年に18%へと半減。なかでも日本は2000年の15%から24年に4%と4分の1に急減。日本の世界経済における衰退振りが顕著である。
かかる日本経済の衰退に関し、日本政府も財界も真剣に対応策を打ち出していないことは誠に慙愧に耐えない次第だ。90年始めには一人当たりGDPが米国に次いで2位を占めていた日本が24年には38位に落ち込み、カリブのプエルトリコ(30位)、バハマ(32位)、アジアのブルネイ(33位)、台湾(34位)、韓国(35位)、欧州のスペイン(36位)、スロべニア(37位)に差を付けられつつある。このままでは50位、三流国に落ち込むのは時間の問題とみられている。日本の早急なる対策が強く要請される次第だ。
一方、2001年にWTO(世界貿易機関)に加盟した中国は、豊富な労働力を生かし、「世界の工場」となり、24年にGDPは世界の17%に達しG6のGDPに肉薄している。米国のGDPは2000年に30%が24年に26%と低下幅は小さい。米一強ともいえるG7内の格差がトランプ氏のG7軽視につながっている面がある。7月11日マレーシアのクアランプールで開催のASEAN地域フォーラム(ARF)では、米中ロの大国間対立が平和と安定を損なわないよう、「対話から、具体的な行動の実践への前進」を求めた。
日本は中国が人類運命共同体を目指し鋭意推進中の広域経済圏構想「一帯一路」や「アジアインフラ投資銀行」への積極的な協力、8月の横浜での第9回TICAD(東京国際アフリカ開発会議)で2050年に25億人に達するアフリカとの協力強化。WTOを補強する意味でのCPTPPの拡大などトランプ高関税への対応策を真剣に考究すべきであろう。